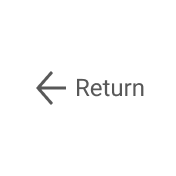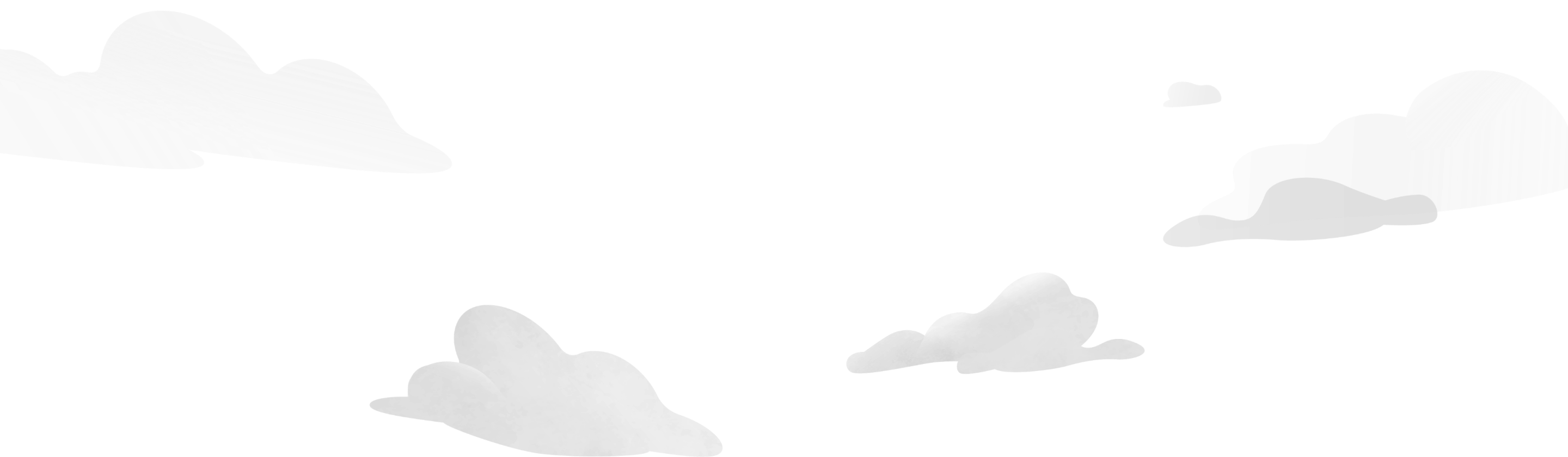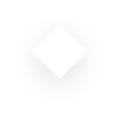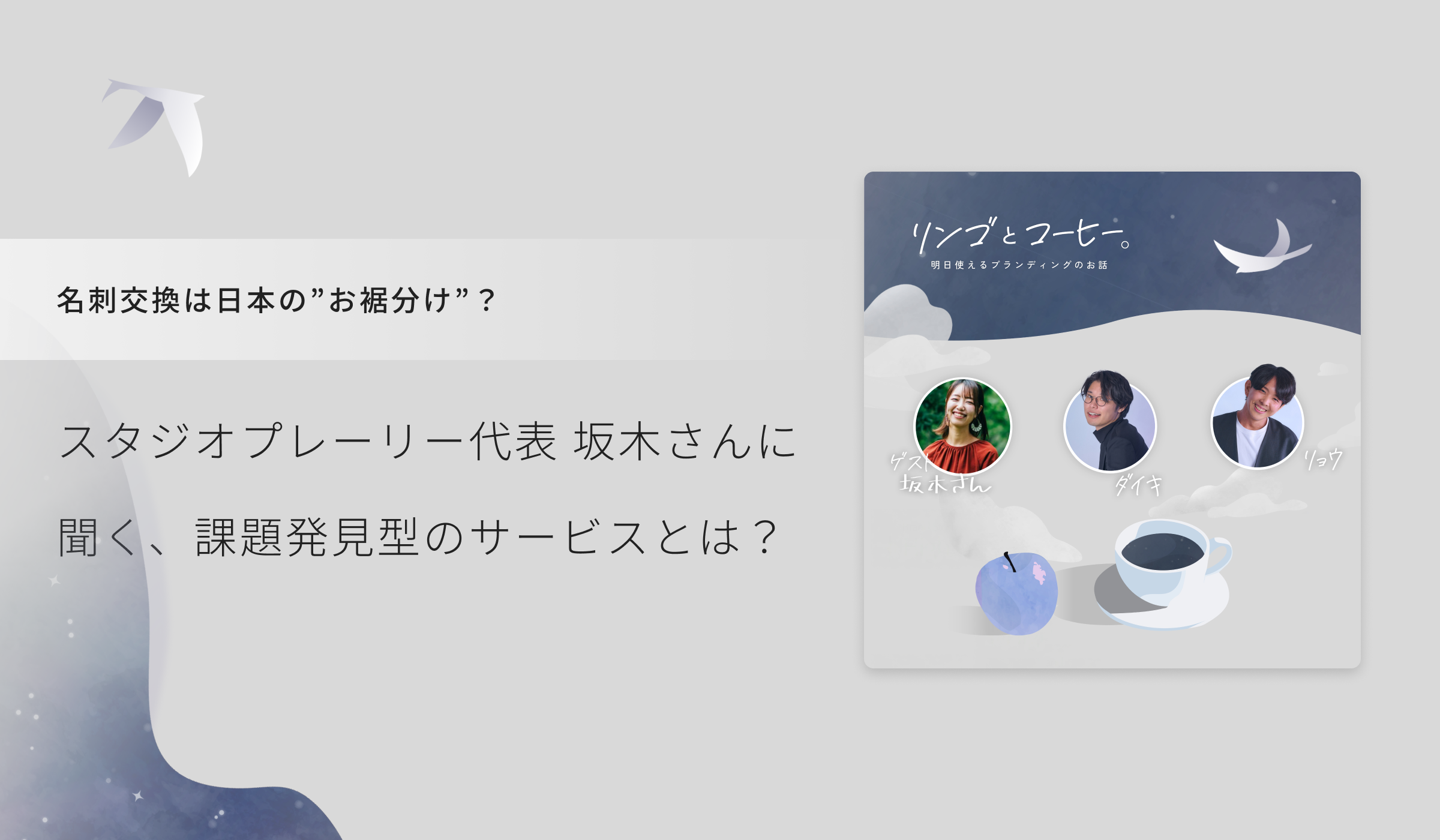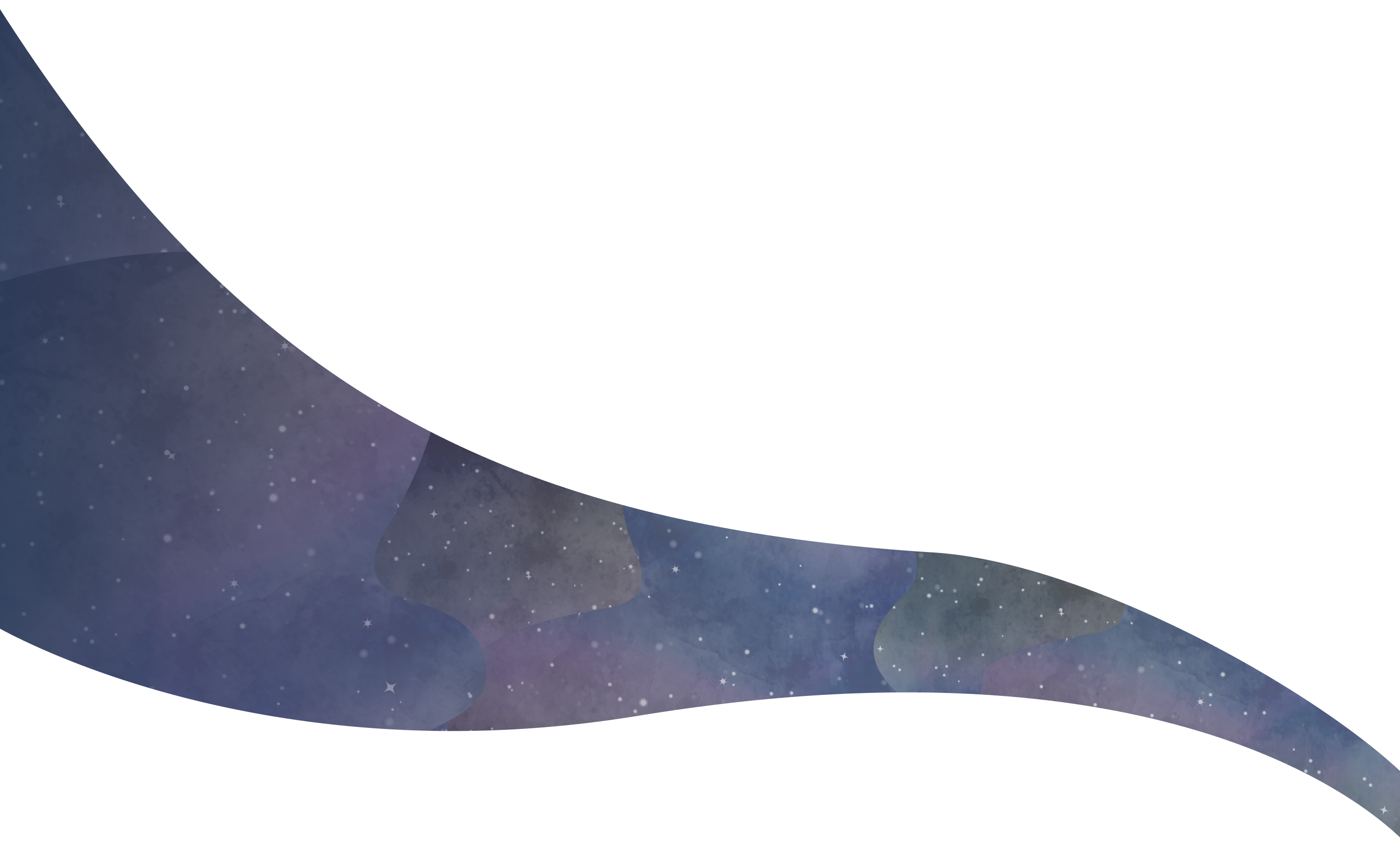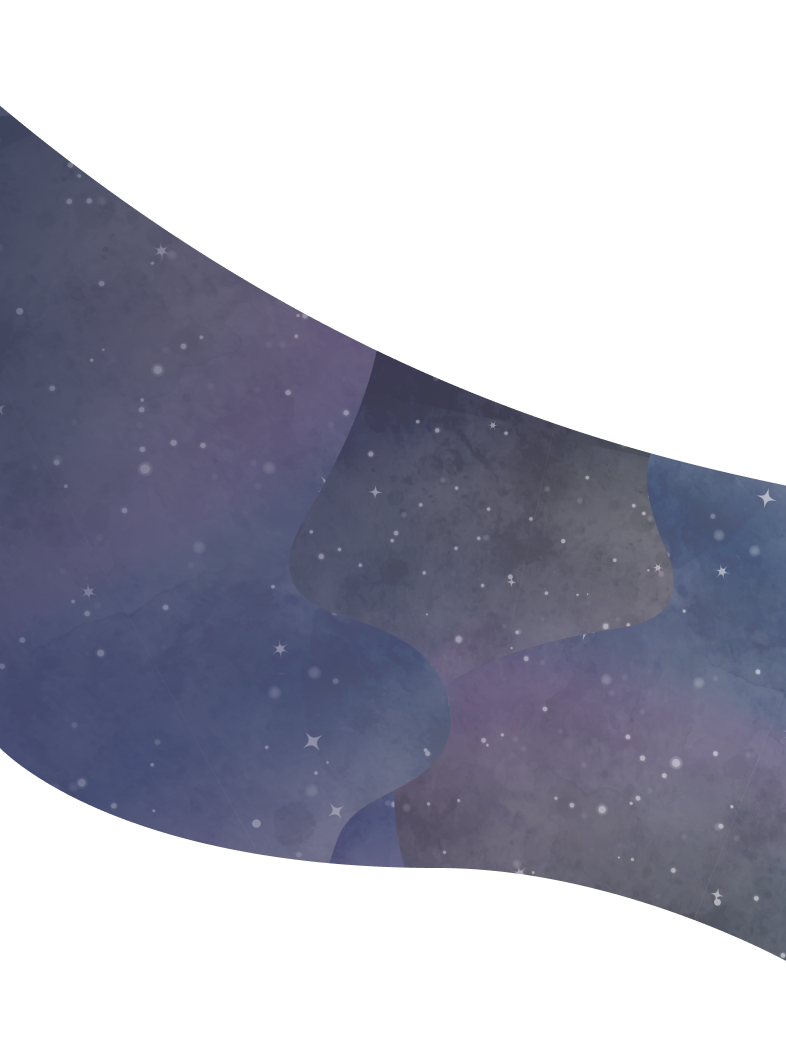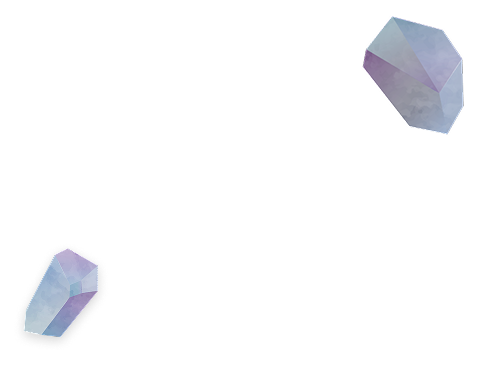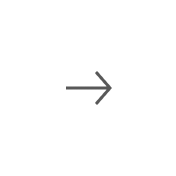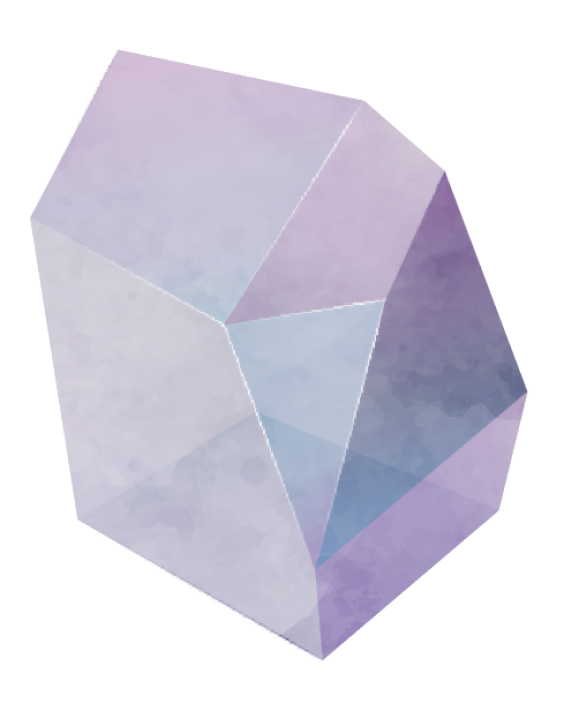
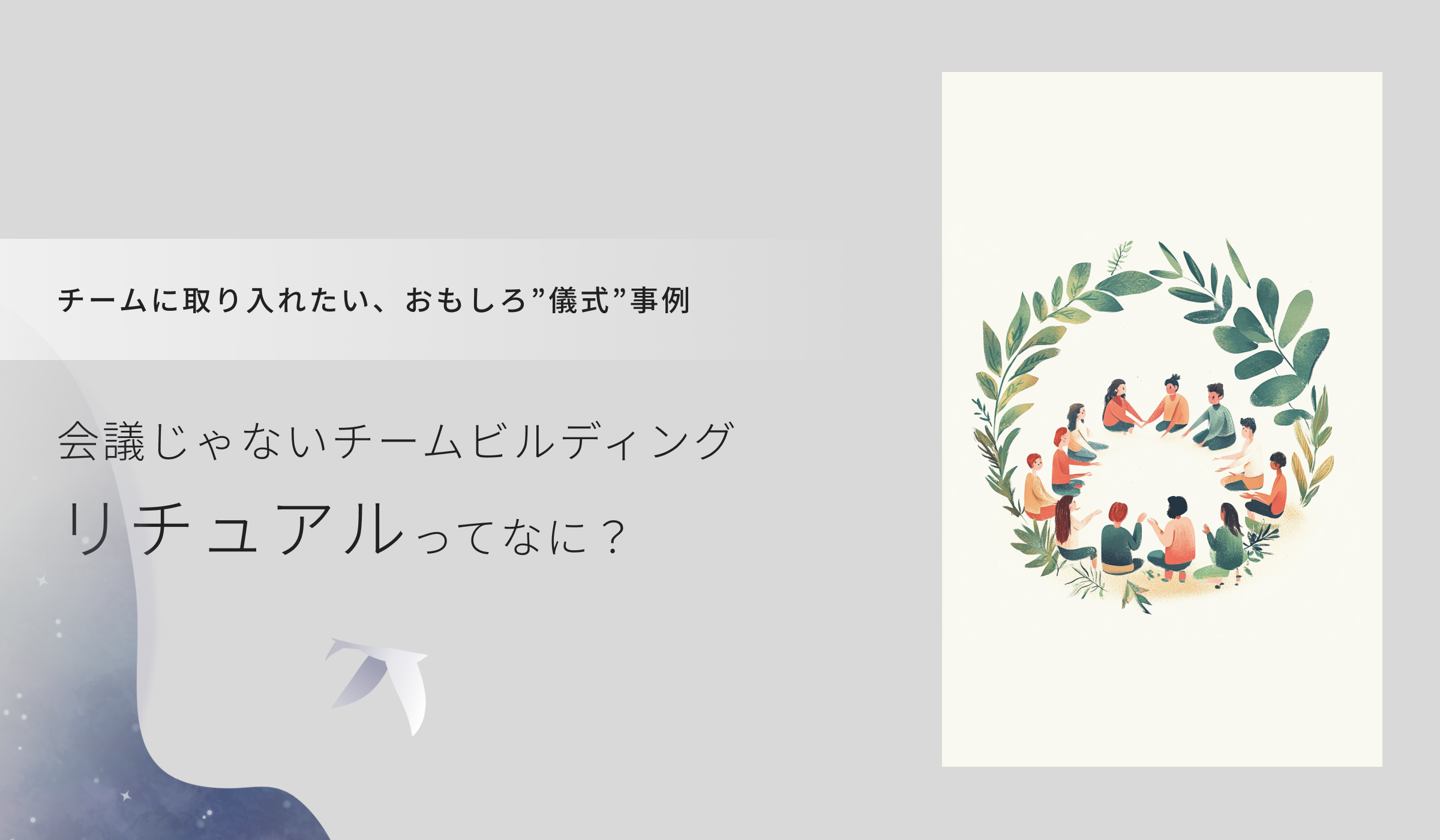
そのリチュアル(儀式)、効きます。チームを元気にする“ちいさな魔法”たち
「合言葉」「差し入れ」「もくもく会」「ノー残業デー」。
皆さんのオフィスの日常には、実はたくさんの小さな“儀式”が潜んでいます。
このようなアクションの効果は数値ではわからないかもしれませんが、チームの空気感を整えたり、気持ちのスイッチを入れたり。じわじわと効いてくるんです。
今回は、そんな“リチュアル(儀式)”の力に注目して、いくつかのちょっと面白い世界の事例を紹介させて欲しく思っています。
リチュアル(儀式)とは
チームの一体感を高め、組織のカルチャーを育てるために有効なのが「リチュアル(儀式)」です。リチュアルとは、日常の中に組み込まれたある種の習慣のこと。
リチュアルは、数値では測れない「空気」や「信頼感」を醸成し、社員のモチベーションやエンゲージメント向上に寄与します。
重要なのは、トップダウンで押し付けるのではなく、メンバーの声から自然発生的に生まれること。自分たちの文化を、自分たちの手で育てる。それこそが、長期で機能するインナーブランディングの姿なのです。
メンバーからの自然発生、どうやって促す?
自然発生する文化を作ること自体が少し難易度が高いと思います。以下の意識は効果があるでしょう。
1. 小さな「余白」を意図的に設ける
たとえば定例会議の終わりに5分だけ雑談タイムを設ける、Slackに「#たわごと部屋」などのチャンネルを作るなど、意見や感情が自然にこぼれる“余白”をつくる。
2. すでに存在している習慣に気づく
無意識のうちに繰り返している言葉や行動があれば、それを「名前をつけて可視化」することでリチュアル化できます。たとえば「Slackで毎朝『おはよう』スタンプをつける」なども、立派な文化の種です。いくつか書き出してみると発見があるかも!
3. メンバーの発案を拾ってみんなで試す
そもそもの文化醸成の一つですが、誰かが「こういうの、やってみません?」と提案したときに、否定せず、まずやってみる。
その“試してみる空気感”が、文化を耕す土壌になります。発案を出すためにも様々な事例をチーム内に共有しておくことはアイデアの種になるでしょう。
事例01:パワーアップスイッチ
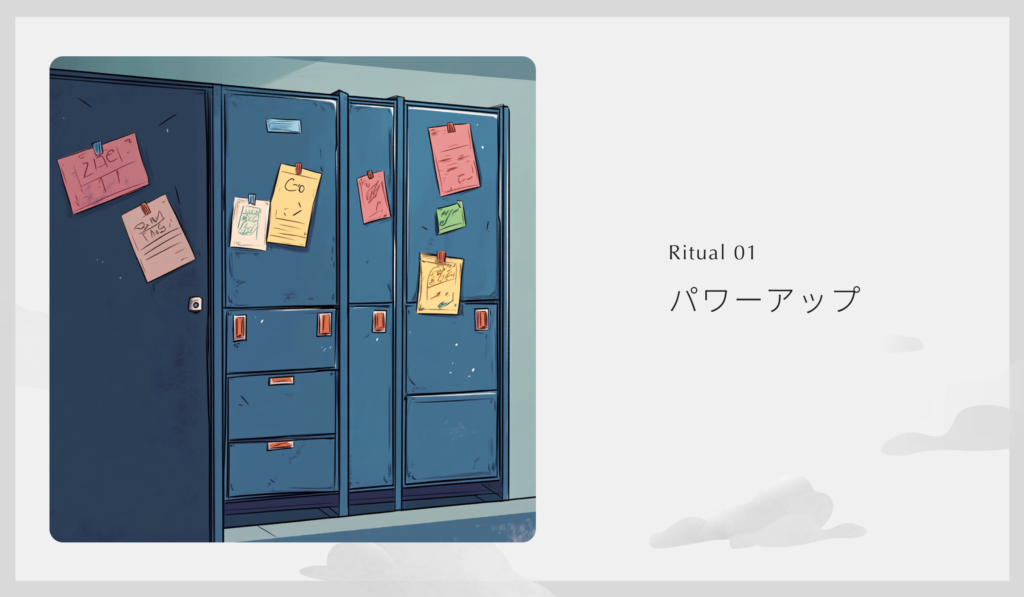
ノートルダム大学アメフトチームのロッカールームにある貼り紙には「Play Like a Champion Today(優勝者らしくプレーしろ)」と書いてあります。
選手たちはこの貼り紙に触れてから試合に出る。書いてある紙を見るのではなく触れる。まるでプラセボ的な心のスイッチ。
それが彼らに、静かなる闘志を宿らせるのです。
事例02:幹部会議をみんなでドライブにする

コロンビアの家電会社アセブのCEOシプリアーノ発の事例です。
アセブ、ある売り上げ難航の時期。シプリアーノ自身で現場にアイデアを求めた際、顧客の声を聞いた。その上での施策実行は売り上げへのポジティブな影響がありました。
この過程を社内に取り入れる方針を切りたかったが、他の幹部らは現場からは遠い。
そこで、四半期ごとの幹部会議を、会議室ではなくみんな車で現場への特別出張に置き換えたのです。
そこからカルチャー自体も様変わり。
幹部のマインドにも顧客中心の考え方が広がり、意思決定の最後に顧客の声を聞くのではなく、顧客の声を中心とした施策立案が出るなど、より良い文化を形成できたとのこと。
また、現場側も幹部のことを「あまり手を動かさない」と印象があったのが、冷蔵庫を運ぶのを手伝うなどの行動から印象が変わったとのこと。
日本企業でも幹部層に対しての懸念があるところはやはり現場で手伝ってもらうのがいいですよね。内部の結束を高める効果も結果としてあったとのことです。
発案者のシプリアーノは元々バックパッカーだったということもあり、現場でリアルな声を聞くことの大切さを知っていたとも言えます。
そのため、この事例から形だけ真似ても意味はない者の、顧客の満足度が重要と気づいているメンバーからの発案であれば、手法としては効果があるかもと思います。
事例03:チーム健康診断
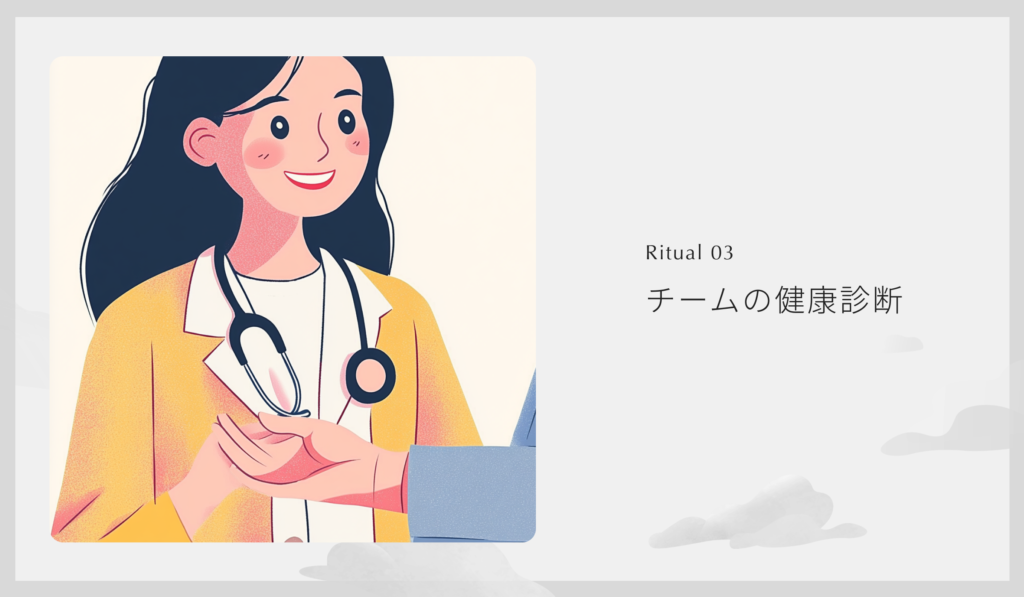
Web、アプリ開発者なら多くの人が使っているJiraの運営会社アトラシアンの事例です。
チームの困りごとや課題などを、チームからチームへ相談することができる儀式(対外的にもメニューが出てますね。詳しくはこちら)。
相談した場合は次までに具体的なやるべきことを決めて解散するというアクション。各チームがお互いに緊急度の高い課題を抱えていることを知る仕組みとして有効かもしれません。
基本、各部署にはその部署のKPIがあり、固定の役割があるためお互いの情報が入りづらい構造になると思います。それを健康診断儀式として場を設けるだけでも、お互いの課題や普段の業務を想像した上で行動ができるようになると期待できそうです。
事例04:対立タイトル焼き払い

これはまたそれっぽい儀式。
対立が発生した議題があった場合その内容を付箋に書き、議論が終わった際にはその付箋を燃やすという儀式。
燃やすという象徴的行為は古来より使われていたが、そこで終わり、という連想をさせるため、チームの前進に効果がある。火の力で“浄化”される感覚って、どこか本能的ですよね。
※もちろん、安全第一で!
発案はmatter-mind-studioのリリアントン(マタースタジオの記事は他も面白いよhttps://medium.com/matter-mind-studio)
事例05:感謝カード

スタバでは、スタッフルームの壁に、従業員の名前とともにカード入れがある。
カードの柄も多くあり(しかも可愛い!)、そこに気づいた他の人の良いポイントを記載して入れておくというもの。
従業員側はプラスアルファの行動をしやすくなるし、アクション自体へのインセンティブとしてワクワクした働きをもたらす。
まとめ:小さな“儀式”が文化を育てる
これらのリチュアルに共通しているのは、「見えない効果を信じて、続けること」。
メンバーの心に火を灯し、チームの関係性を少しずつ耕していく。インナーブランディングの文脈で支援してる時って、その後の浸透フェーズでつまづく企業が多く見受けられます。
浸透させるためにメンバーたちが自発的に動ける仕組みが重要で、上からVisionはこうです!といったところでなかなか浸透しないもの。
そこで、こういった儀式をいくつか取り入れてみて、社員たちが他のアイデアもあります!というような発案ができる風通しを作ってみてはいかがでしょうか?
参考書籍:「儀式」で職場が変わる――働き方をデザインするちょっとヘンな50のアイデア
Podcastでも配信しています!